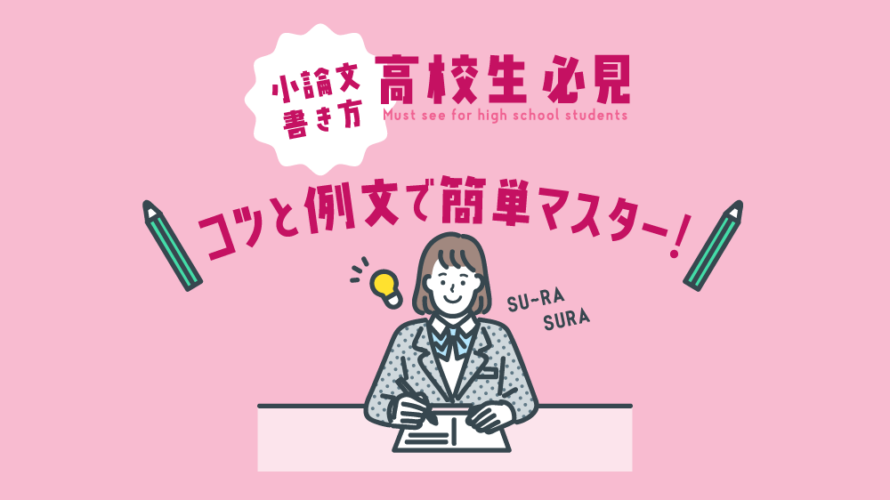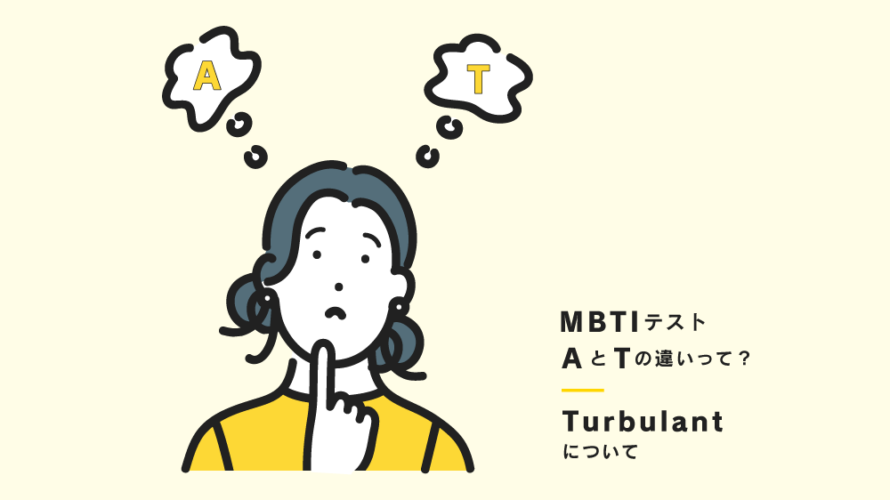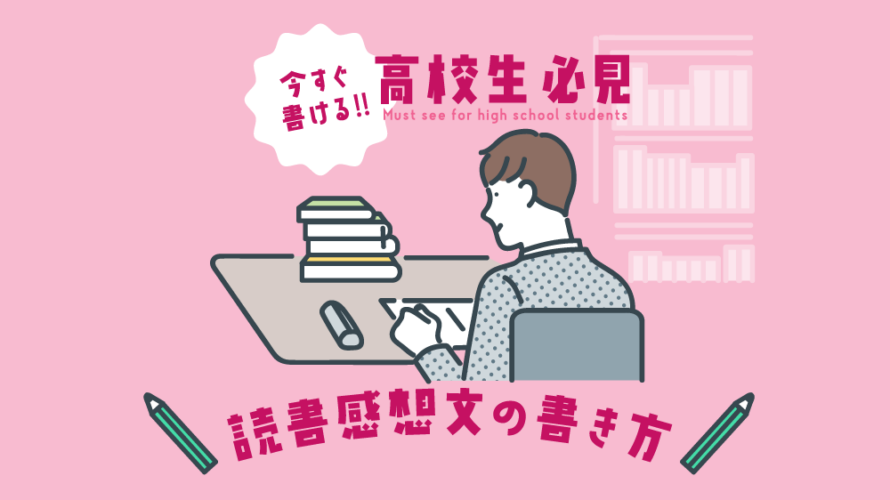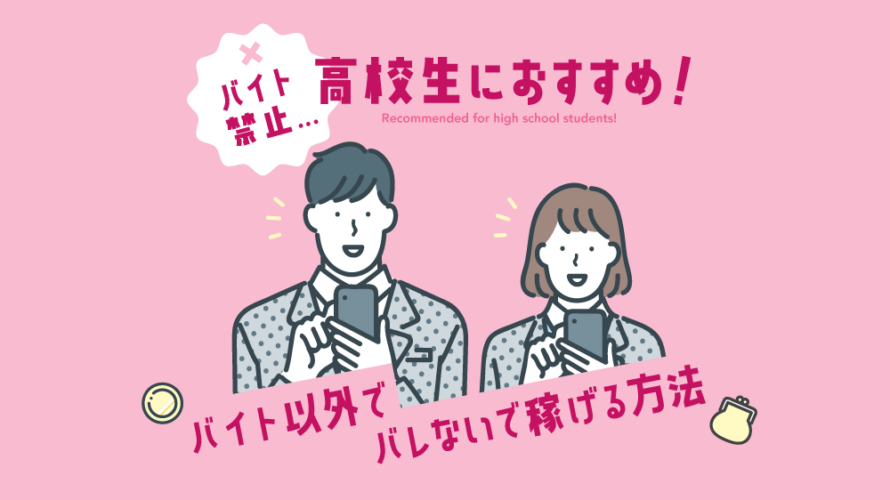【高校生必見】小論文の書き方|コツと例文で簡単マスター!
- 📅 投稿日 2020年01月21日│最終更新日 2024年12月16日
- 📁 勉強
この記事は約 5 分で読めます。
小論文という言葉を聞いて、論文なんて難しそうと苦手意識を持っている方もいますよね。
高校に入学する際の推薦入試に出題される場合もありますが、多くの高校生は大学や短大、専門学校の受験を前にして、はじめて小論文に向きあうのではないでしょうか。
入試などで小論文を書かなければいけないけれど、どう勉強したらいいかわからない…小論文のコツや書き方があるって聞いたけど、調べてもいまいちわからない…そんな方も安心してください!小論文はコツさえつかめば簡単にマスターすることができるんです!
今回は小論文の書き方、書く時のコツについて、わかりやすくご説明します!
小論文のコツって?
小論文のコツはズバリ!まず、「構成から考えて書く」ことです。
問題文を読んだ後、時間がないからと言って焦ってすぐに書き出してしまったりしていませんか?とりあえず書きながら考えよう!と無計画に書き始めるのはちょっと危険です。
小論文はすぐに書き出すのではなく、先に構成を考えてから書くことが重要なんです!
無計画に書き始めると、完成までに時間がかかるだけでなく、文章に一貫性がなくなってしまいます。
小論文で大切な評価ポイントは「客観的で一貫性があること」です。
中学生の小論文であれば、自分の考えを素直に表現することが重視されるのに対し、高校生が大学受験などで書く小論文は、単なる知識の羅列ではなく、より高度な論理的思考力と自分の考えを表現する力が問われます。
そのポイントを押さえるためにも、今回お教えする小論文のコツ「構成から考えて書く」をしっかり意識してから問題に挑戦してみてください。コツがつかめたら、小論文はもうマスターしたも同然です!
自分に合った学校を探してみる
作文と小論文と志望動機の違いとは?
そもそも作文と小論文、志望動機は何が違うのかご存じですか?
この3つは書く内容に大きな違いがあります。
◆作文・小論文・志望動機の大きな違い
- 作文は自由に感想を書くもの
- 志望動機はどうしてその学校を希望するか、入学後のプラン・展望などを書くもの
- 小論文は自分の主張を論じて読み手を説得するもの
小論文では自分の主張を論じて読み手を説得しなくてはいけないため、ただの感想文や志望動機を書かないよう注意が必要です。
小論文は単なる好き嫌いや感想を書くものではありません。あくまでも、出されたテーマや課題に対しての自分の主張を述べ、「なぜそう考えたのか」という理由を明確にして論理的に説明することで、相手を説得する文章のことです。
作文は構成が自由であり、美しい比喩表現などが評価されるかもしれませんが、小論文では文学的表現は全く必要ありません!文学ではなく説明文だと心得ましょう。
入試問題であれば、その設問に対応した「意見(主張)」とその「理由(論拠)」が書かれていればよく、そしてそれが書かれていることで小論文として認められるのです。
自分に合った学校を探してみる「課題文型」小論文と「テーマ型」小論文の違い
小論文に多い出題形式に、「課題文型」と「テーマ型」があります。
小論文のテーマは、幅広く設定されることが多く、「現代社会における○○の役割」や「○○について、あなたの考えを述べなさい」といった形式が一般的です。
まず、与えられたテーマをじっくりと読み込み、どのような視点から分析すれば、自分の考えを深掘りできるのかを考えましょう。
◆課題文型小論文
「課題文型」とは、与えられた文章を読み、設問に沿って自分の考えを述べる形式で、大学入試の小論文で出題の多い形式です。
「この文章を踏まえて、あなたの意見を述べなさい」などの出題文になります。意見とは別に、要約を求められる場合もあります。
また、文章ではなく図やグラフなどをもとに自分の意見を述べる場合は「資料解釈型」といわれます。「この文章を踏まえて」や「課題文の論点を参考に」というところがポイントで、まず文章を読解し、設問者の意図を読み取り、それに対応した文章にしなくてはなりません。
◆テーマ型小論文
「テーマ型」とは、何らかのテーマだけが提示されて、それについての意見を述べる小論文の出題形式です。
「~について論じなさい」などの出題文となり、テーマについての賛否や自分の意見を論理的にまとめます。「課題文型」よりも制約が少ないようにも思えますが、抽象的なテーマの場合、何について述べるのかの実質的なテーマは自分で思いつく必要があります。
入試の場合は、試験を受ける学科等に関係する課題やテーマが出題される場合が多いので、志望する分野の情報に常日頃から触れ、それに対する自分の考えを持っておくことが重要な対策になるでしょう。
小論文の構成とは?例文付きで詳しく紹介
本論→具体的な主張の理由
結論→まとめ
最初に小論文を書くコツは「構成から考えて書く」だと申し上げましたが、ここではもっと詳しくご紹介します!
基本の小論文の構成は「序論・本論・結論」で成り立っています。
小論文は、単に自分の考えを書き出すだけではなく、読者に分かりやすく伝えることが求められます。段落ごとにテーマを分け、論理的な流れで文章を構成しましょう。
はじめに、自分の主張を明確にし(序論)、以下に根拠となる情報を示し(本論)、最後に再度主張をまとめる(結論)といった、基本的な構成を意識すると良いでしょう。
この3つに書くべきことを当てはめていき、構成を考えてみましょう。
◆小論文の構成を考えるコツ
小論文の一般的な構成を2パターン紹介します。自分に合った構成を選んで練習しましょう!
1. 序論・本論・結論で書くパターン
王道のパターンです。基本的にはこの構成で考えるのがおすすめ!
序論(自分の主張):「○○だから、××するべきだ」
本論(主張の理由):「なぜなら~~だからだ」
結論(まとめ):「よって、私は××するべきだと考える」
2. 序論・反論・持論・結論で書くパターン
反論を挟んでより自分の主張を際立たせる方法もあります。持論の部分で反論を打ち消すことで、自分の主張を強調します。
序論(自分の主張):「○○だから、××するべきだ」
反論(異なる意見):「しかし、××すると、▲▲になるという意見がある」
持論(自分の意見の強調):「▲▲になるには■■が必要だ。だが、××することで■■を防ぐことができる」
結論(まとめ):「よって、私は××するべきだと考える」
慣れてきたら状況に合わせて使ってみてください♪
また、どちらも書き出しに当たる序論がとても大切です。書き出しには問題提起だけでなく、結果にあたる自分の意見をしっかり書くようにしましょう!最初に主張を明確にすることで、読み手側にとっても全体の文章が読みやすくなります。
これだけで評価がぐっと上がります!提出前には必ず確認してくださいね。
おまけ:要約文のコツ
小論文と一緒に文章の要約を求められることもあります。
要約のコツは「短文を心掛け、具体例をカットすること」です!
意識するべきポイントをご紹介します。
- 短文を心掛け、接続詞を正しく使うこと
- 具体例はカットし、内容にダブりがないか確認する
小論文の注意点と評価ポイント
最後に小論文を書く際の注意点と評価されるポイントをご紹介します。小論文のコツと合わせてチェックしてくださいね。
小論文を書くうえでの注意点
- である調(ですますはNG)
- 指定内の文字数で書かれているか
- 文字数が極端に少なくないか(9割を目指して書こう)
- 練習の際は書いたままにしない(必ず第三者に添削してもらおう)
小論文の評価ポイント
- 書き出しでしっかりと自分の意見を述べていること
- 文章の内容が客観的で一貫性があること
小論文のよくある間違いと対策
- 「同じ」言葉の繰り返し:
別の言葉に言い換えたり、類語を用いたりして、表現にバリエーションを持たせましょう。 - 「脱線」してしまう:
テーマから脱線しないように、常にテーマに沿って文章を書くことを意識しましょう。 - 「結論」が曖昧:
結論は、論理的な流れの最終地点であり、最も重要な部分です。簡潔かつ明確にまとめましょう。
小論文では、字数制限や記述形式など、様々なルールが設けられています。減点にならないために、注意深く問題文を読み、指示に従って記述しましょう。
入試で課される文字数は大学で800~1,200字以内、短大で600~800字以内、専門学校で400字以内が多いようです。
何文字以内と指定がある場合は一文字でも超えると失格になってしまうので、句読点含めしっかり確認してください!
テーマを深堀する訓練をしよう
受験生の場合、試験当日にテーマが示される場合も多いですが、事前にテーマが提示されることもあります。作成に時間がある場合は、ニュースや書籍、インターネットなど様々な情報源からデータを収集し、根拠となる情報を集めましょう。社会で起きている出来事や専門家の意見などを参考にしながら、論理的な思考を養います。
思考力を培うためには、「なぜ?」を問い続けるが大切です。集めた情報をもとに、なぜそのように考えるのか、なぜその結論に至ったのかを自分自身に問い続けましょう。体験に基づいた意見や、学習を通して得た知識を結びつけ、一つの結論へと導くことが重要です。
この経験を積み重ねていくことで、テーマを見たときに主張が浮かびやすく、根拠も示しやすくなります。小論文を書くコツも身についていくといえるでしょう。
まとめ:小論文を書く上でのポイント
最後に、小論文を書くためのポイントを改めてまとめます。
- 「人」を意識して書く:
小論文は、単に自分の意見を述べるだけでなく、読者にいかに自分の考えを理解してもらうかが重要です。読者の立場に立って、分かりやすく、説得力のある文章を心がけましょう。 - 「答え」を導き出す:
小論文のテーマに対して、ただ自分の意見を述べるだけでなく、論理的な思考に基づいた「答え」を導き出すことが求められます。 - 「例」を効果的に使う:
抽象的な概念は、具体的な「例」を用いて説明することで、より理解しやすくなります。 - 「ルール」を守る:
小論文には、字数制限やテーマからの逸脱など、様々な「注意」すべき点があります。事前にしっかりと確認しておきましょう。 - 「指導」を受ける:
学校の先生や塾の先生など、経験豊富な人に「指導」を受けることは、上達への近道です。
ここまで小論文のコツについて説明してきましたが、学んだコツを活かすには実際に手を動かして練習することが何よりも大切です!何回も練習することで自信がつき、実際の入試では落ち着いて試験を受けられるようになります♪当日までしっかりと繰り返し練習して試験に臨みましょう!
小論文は、受験において高い得点につながるだけでなく、社会に出てからも役立つスキルです。この記事を参考に、ぜひ小論文の練習をしてみてくださいね。
自分に合った学校を探してみる

 専門学校を探す
専門学校を探す
 職種から探す
職種から探す
 特徴から探す
特徴から探す
 学費制度から探す
学費制度から探す
 資格・職業を考える
資格・職業を考える