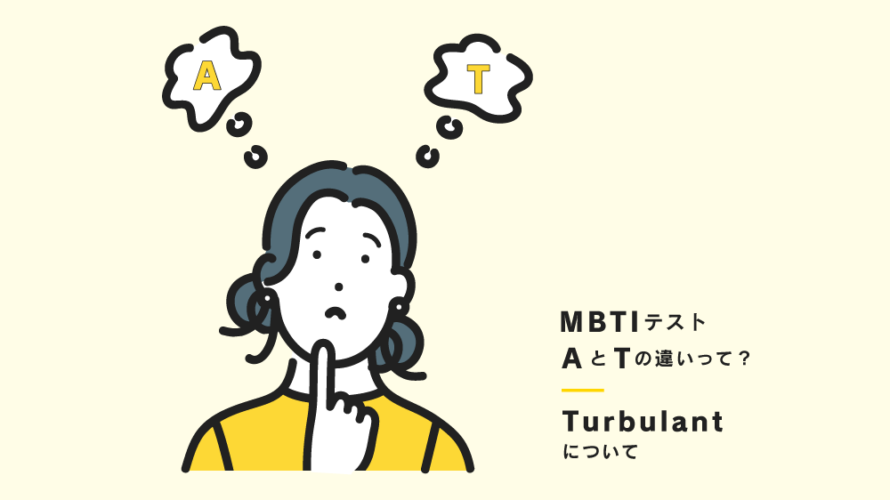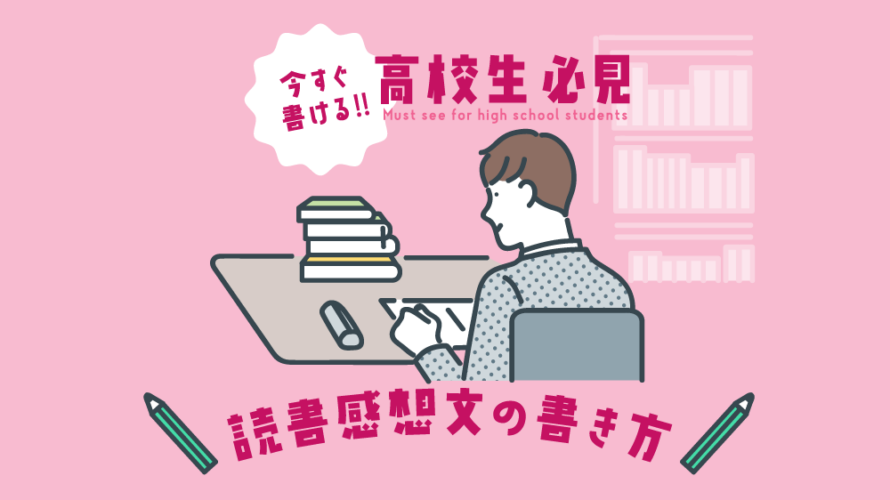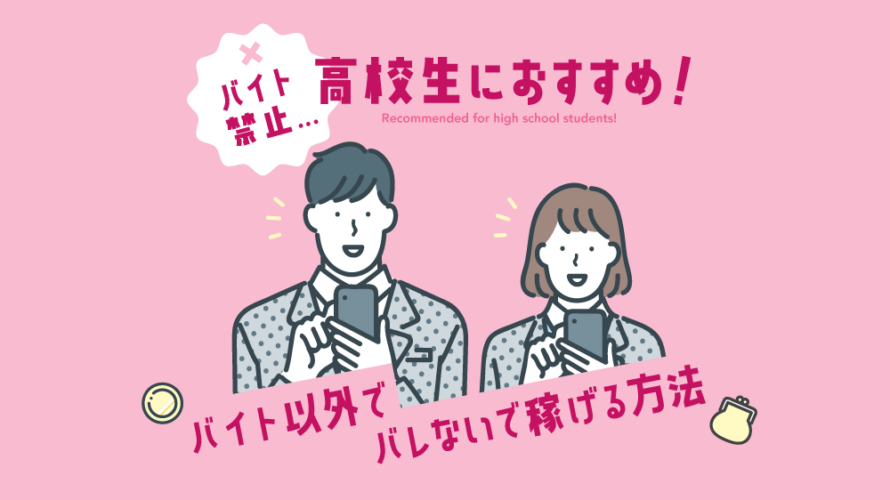翻訳家になるには?仕事内容や役立つ資格、向いている人の特徴を紹介!
- 2020.09.15
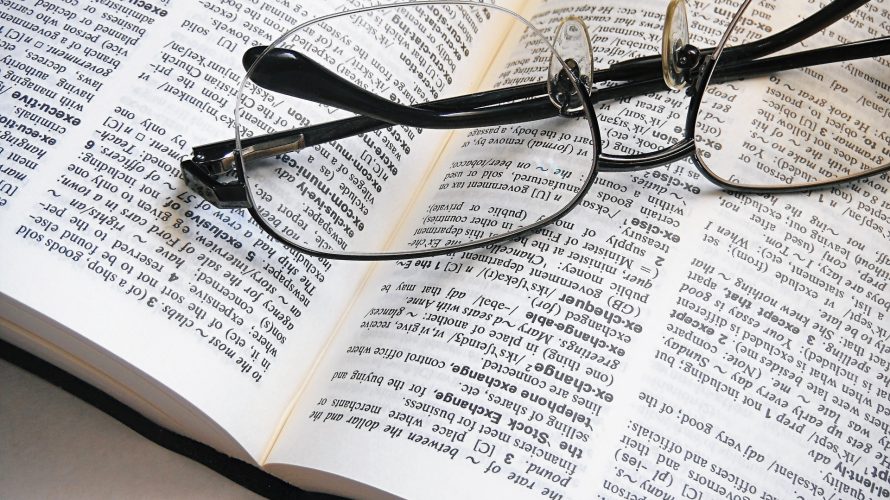
記事をシェアする
この記事は約 5 分で読めます。
外国語で書かれた文章を日本語に訳す「翻訳家」。言葉の壁を越えて、人々に情報を伝える、文化を繋ぐ、そんな魅力的な仕事に憧れる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、翻訳家になりたい方のために、仕事内容からなり方、役立つ資格、就職先、年収、将来性、そして翻訳家に向いている人の特徴まで、詳しく解説していきます。関連する職業や翻訳家になるための専門学校情報も紹介するので、進学やキャリアアップを検討している方もぜひ参考にしてください!

翻訳家ってどんな仕事?
翻訳家とは
翻訳家とは、ある言語で書かれた文章を別の言語に翻訳する職業です。日本では、海外の小説や論文を多くの人が楽しんだり理解したりするために、さまざまな外国語で書かれた文章を適切な日本語に訳されています。
そんな翻訳家は、大きく「文芸翻訳家」「実務翻訳家」「映像翻訳家」の3種に分けられます。
- 文芸翻訳家
小説や雑誌、歌詞などといった海外の文芸作品を日本語に訳す翻訳家。作品の世界観や著者の意図に沿った翻訳表現が求められます。 - 実務翻訳家
外国語で書かれたビジネス関連の文書を日本語に訳す翻訳家。実務翻訳家が翻訳を行う文書の中には、科学や医療などに関するものもあるため、専門的な知識が求められます。 - 映像翻訳家
映画やドラマといった映像作品の音声を日本語に訳す翻訳家。字幕による翻訳と、吹替えによる翻訳があり、作品の世界観や登場人物のキャラクターに沿った翻訳表現が求められます。
人々が海外の文芸や映像を楽しんだり海外とのビジネスを行なったりするために翻訳は必須であり、翻訳家は優れた外国語のスキルを生かし、世界の文化と日本を繋げています。
翻訳家の仕事内容とは
翻訳家の仕事は、外国語で書かれた文章を日本語に訳することです。翻訳家が翻訳を行う文章の例には、以下のようなものがあります。
- 小説
- ノンフィクション作品
- 雑誌
- 児童書
- 歌詞
- ビジネス書
- 契約書
- 学術書
- 研究論文
- マニュアル
- 映画
- ドラマ
- ドキュメンタリー
翻訳家はこのような文芸作品や文書、映像の翻訳を手掛けます。単に言葉を置き換えるだけでなく、原文の意味やニュアンスを正確に理解し、読者に自然に伝わるように表現することが求められます。
書籍、論文、契約書、ウェブサイト、映像作品など様々な媒体で翻訳を行いますが、おもな仕事内容は以下の通りです。
- 翻訳: 原文を理解し、正確で自然な文章に翻訳する。
- 校正: 翻訳された文章の誤りや不自然な箇所をチェックし、修正する。
- リサーチ: 専門用語や文化背景などを調べる。
- 顧客とのやり取り: 翻訳内容に関する打ち合わせや修正対応を行う。
また、翻訳家は外国語を日本語に訳すだけではなく、外国語を日本語に訳すこともあり、その外国語は英語だけにはとどまりません。中国語やフランス語、ドイツ語など世界のさまざまな言語を理解し、日本語への、もしくは外国語への翻訳を行なっています。
翻訳家になる方法
翻訳家になるための特別な資格や免許はありません。未経験からでも、実力次第で翻訳家として活躍することができます。
しかし、翻訳には外国語の高いスキルが必要になるため、翻訳家を目指すのであれば、まずは外国語大学や大学の外国語コース、または翻訳の専門学校で学び、外国語スキルを身に付けるのが一般的でしょう。
また、翻訳家になる主な道のりとしては、以下の方法があります。
- 一般企業への就職
企業翻訳部門や法律事務所などに就職し、実務翻訳を担う。 - 翻訳会社への就職
翻訳を専門に請け負う会社に就職する方法。実務翻訳の需要が多い。 - フリーランスの翻訳家として活動
フリーランスとして独自に活動する他、翻訳会社に登録して仕事の斡旋を受けるケースも。文芸・映像翻訳の需要が多い。
このように、就職先や働き方によって、請け負う翻訳の種類は変わります。
また、文芸・映像翻訳の依頼が多いフリーランスの翻訳家を目指す人は多いですが、就職する場合に比べ仕事が安定しにくいため、副業を持って、もしくは翻訳を副業として活動する人もいます。
翻訳家になれる学校を探す
翻訳家に求められる資格や試験
翻訳家には、必須とされる資格はありません。資格よりも、外国語の翻訳スキルが重視されます。
ただし、スキルアップや就職活動に役立つ資格はいくつかあります。
- 実務翻訳検定: 実務翻訳の能力を測る検定試験。
- JTA公認 翻訳専門職資格: 日本翻訳協会が認定する資格。
- TOEIC・英検: 英語力を証明する資格。
実務翻訳検定
翻訳実務検定「TQE®」は、サン・フレア アカデミーが実施する、産業翻訳分野のプロの翻訳者の能力を認定する検定です。
試験では、限られた時間内に、商品として価値のある訳文を作り出せる能力を評価します。合格すると「翻訳実務士」と認定され、プロの翻訳者としてサン・フレアに登録することができます。
JTA公認 翻訳専門職資格
JTA公認 翻訳専門職資格は、一般社団法人日本翻訳協会が実施する、翻訳のプロフェッショナルの能力を総合的に審査し、認定する資格です。この資格を取得するには、JTA公認翻訳専門職資格試験に合格し、さらに翻訳実務経験2年以上の実績審査に合格する必要があります。
試験は、英語と中国語の2つの言語に対応しており、科目ごとに合否判定とグレードが示されます。試験科目は、翻訳文法技能試験、翻訳IT技能試験、翻訳マネジメント技能試験の3つに加えて、英語部門では出版翻訳能力検定試験またはビジネス翻訳能力検定試験の1分野、中国語部門では中国語翻訳能力検定試験の1分野の試験が課されます。
この資格を取得することで、翻訳者としてのスキルアップを図り、キャリアアップにつなげることができます。また、自身のWebページや履歴書などに資格を記載することで、公的な資格証明として活用することができます。
TOEIC・その他の外国語検定
外国語に関する資格の取得は、翻訳スキルを高めるためにも役立ちます。そして、外国語に関する資格の中でも代表的なものとして挙げられるのが、「TOEIC」です。
「TOEIC」は英語のコミュニケーション能力を測る英語資格であり、グローバルスタンダードとして多くの国で実施されています。翻訳家を募集する企業の中には、「TOEIC」のスコアを条件に挙げる企業もあり、日本でもステイタスの高い英語資格として広く知られています。
そんな「TOEIC」の試験には、以下の5つのコースがあります。
- TOEIC Listening & Reading Test
- TOEIC Speaking & Writing Tests
- TOEIC Speaking Test
- TOEIC Bridge Listening & Reading Test
- TOEIC Bridge Speaking & Writing Test
この中でもメジャーなものは「TOEIC Listening & Reading Test」です。「TOEIC Listening & Reading Test」は英語を聞く力・読む力を測るテストであり、社会人のキャリアアップや学生の就活にも役立つものとして、多くの人に受験されています。もちろん、翻訳家の仕事にも役立つでしょう。ただし、仕事や就活に役立てるためには、かなりの高スコアを取得する必要があります。
また、「TOEIC」以外の外国語に関連する資格には、「英検」や「中国語検定」、「フランス語検定」、「ドイツ語技能検定」などの各種外国語検定があります。翻訳を請け負う言語によって生かせる資格の種類は変わりますが、このような資格を取得しておけば、就職や仕事の取得、実務に役立てられるでしょう。
また、法律や医療、科学など、翻訳を手掛ける分野の資格が役立つこともあるため、個々の翻訳家によって業務に関連する資格には違いがあります。
今後の翻訳家の将来性
近年、AI技術が発展し、専用端末やスマートフォンなどで簡単にAIによる翻訳が行われるようになりました。この翻訳方法は多くの人に利用され、またAIによる翻訳の質も徐々に向上しつつあります。今後も、手軽に行えるこのような翻訳方法は、さまざまな場面で役立てられるでしょう。
とはいえ、AIによる翻訳では、まだまだ細かな部分の適切な表現を行えてはいません。世界観やニュアンスなどといった定形に当てはまらない表現は人間ならではのものであり、AIに理解し表現させることは困難なのです。
そのため、特に言いまわしやニュアンスが重視される文芸・映像翻訳の世界において、人間の翻訳家の需要は、今後も一定数保たれるでしょう。
ただし、翻訳家として活躍を続けるためには、外国語スキルはもちろん、それぞれの作品や文書に適した表現を行えるセンスが必要です。このセンスこそがAIには難しい部分であり、翻訳家はこれを磨いていく必要があるでしょう。
翻訳家の就職先
翻訳家の主な就職先には以下が考えられます。
- 翻訳会社
- 出版社
- 広告代理店
- 国際機関
- 企業の海外事業部
翻訳家の就職先は、一般企業か翻訳会社に分けられます。
一般企業の場合は、医療や工業、金融関連の会社や貿易会社、特許関連会社、法律事務所などが例として挙げられます。これらの会社に翻訳家として就職した場合には、契約書やマニュアルなどといった実務翻訳を担当することになるでしょう。ただし、求人数はさほど多くはなく、専門性の高い会社や大企業では、特に高い翻訳スキルが求められます。
また、翻訳を専門に行う翻訳会社に就職した場合も、実務翻訳を担うことが多いようです。翻訳会社は数多くあり、求人も一定数出されています。
さらに、就職はせず、フリーランスとして活動するのもひとつの方法です。しかし、そのためにはスキルや経験、人脈などが必要になるため、まずは会社に就職して翻訳のノウハウを学んでおくと、後の活動が有利になるでしょう。
翻訳家の平均年収・MAX年収
企業に就職して活動する翻訳家の場合、その年収は500万円前後が相場です。ただし、勤める企業の規模やキャリア、専門知識の有無なとによって給与は変わるため、実際の年収幅は広いと考えられます。
また、フリーランスの翻訳家の場合は、仕事量や実績によって大きく収入が変わるため、さらに年収に幅が生じます。ベテランの翻訳家であれば年収1,000万円を超えることもあるようですが、一方で駆け出しの翻訳家であれば収入がほとんどないということもあります。そのため、フリーランスの中には副業を持っている人も多く、翻訳家としてだけで生計を立てることは決して簡単ではありません。
翻訳家に向いているのはこんな人
翻訳家に向いているのは、外国語のスキルが高いだけでなく、外国の文化やマナーにも深い興味や知識を持っている人です。
翻訳は、ただ言葉を訳せばいいというものではありません。それぞれの国の文化によって適した訳が変わることもあります。それを知らないまま翻訳を行なってしまうと、マナー違反になったり相手に不快な思いをさせてしまったりする可能性があります。そのため、翻訳家には外国語と外国の文化に対する知識が必要なのです。
また、読み手を意識した翻訳を行えるスキルも、翻訳家には求められます。専門家には専門家向けの、子どもには子ども向けの言葉があるように、翻訳家には読み手に合わせた言語表現が求められるためです。これができなければ、翻訳された文章の魅力は半減してしまうでしょう。
翻訳家に関連する職業
翻訳家に関連する職業のひとつに、通訳があります。
翻訳家と通訳はどちらも外国語を日本語に、または日本語を外国語に訳す職業であり、その業務は共通しています。しかし、翻訳家は「文字で訳す」、通訳は「口頭で訳す」という違いがあり、それぞれ違ったフィールドで翻訳業務および通訳業務を行っています。
また、著作家や映画監督、脚本家なども、文芸・映像翻訳を行う翻訳家にとっては関係の深い職業です。小説や映画の翻訳においては、それを制作したこのような職業の人々の意図を汲み取らなくてはならないためです。著作家や映画監督などといった制作者への理解が、翻訳家には求められます。
翻訳家に関連するおすすめの専門学校
専門学校では、翻訳に必要な専門知識や技術を体系的に学ぶことができます。また、プロの翻訳家による指導を受けることで、実践的なスキルを身につけることができます。
また、学校に通うことで、他の翻訳者や翻訳を目指す人とのネットワークを築くことができます。これは、今後の仕事やキャリアに役立つでしょう。
そこでここからは、おすすめの翻訳家に関連する専門学校をご紹介します。いずれも翻訳に関連する分野でとても評価の高い学校なので、翻訳家について専門的に学びたいという方には最適な学校です。
グレッグ外語専門学校【東京都目黒区】
◆関連学科:通訳翻訳コース
1964年、グレッグは東京/代々木でスタートしました。
創立から50年以上を迎えたグレッグは、日本のエリートビジネスマンの語学教育をリードし続けてきました。
早稲田国際ビジネスカレッジ【東京都新宿区】
◆関連学科:国際コミュニケーション学科 韓国語コース
総合韓国語では初級からを말하기(スピーキング) 쓰기(ライティング) 읽기(リーディング) 듣기(リスニング)어휘 및 구조(語彙及び構造) を均一に学習、日常生活に必要な韓国語スキルを向上させることを目的としています。
また授業では話す機会を増やし、韓国語が自然と出てくる環境を作っていきます。
早稲田国際ビジネスカレッジの詳しい紹介はこちら
ディライトグローバル専門学校【東京都福生市】
◆関連学科:グローバルコミュニケーション学科
英語とビジネスを学ぶ。
グローバルなビジネス環境において必要とされる基礎的な実務力と応用力、高い語学力を基礎としたコミュニケーション能力の醸成、時代の変化と多様な価値観に対応可能な人材育成を目指します。
ディライトグローバル専門学校の詳しい紹介はこちら
専門学校 東京ビジネス外語カレッジ【東京都豊島区】
◆関連学科:【国際コミュニケーション学科】英語ホスピタリティコース、【国際コミュニケーション学科】日中医療通訳コース
英語とビジネスを学ぶならTBLへ。
グローバル人材を育成するインターナショナルな専門学校です。
東京福祉保育専門学校【東京都豊島区】
◆関連学科:日本語学科、国際IT学科、国際ビジネス学科
「ここまで面倒見てたら先生がもたないよ」と、他校からはあきれられてしまうかもしれません。
でも、たくさんある学校の中からうちを選んでくれた学生たち。
大切に育てたいんです。



記事をシェアする


 専門学校を探す
専門学校を探す
 職種から探す
職種から探す
 特徴から探す
特徴から探す
 学費制度から探す
学費制度から探す
 資格・職業を考える
資格・職業を考える