
小林 桜子さん
2年制モノづくり系
その場しのぎは通用しないデザインの厳しさ
創造社を選んだのは、学校見学会に参加して、真剣にデザインを学べる環境がここにはあると感じたから。他校も見学に行ったけど、ぜんぜん雰囲気が違うと思いました。
デザイン領域を超えて学べることも魅力でした。入学当初、狭い視野でデザイン業界を見ていた私にたくさんの選択肢があることに気づかされました。
見学で感じていた通り、クラスメイトのモチベーションも高く年齢層もバラバラなのでお互いいい影響を受け合えていると感じています。
あと、その場しのぎが通用しないことを2年生になって痛感しています。課題が多いし、とりあえずその場しのぎでその時は「ちゃちゃっ」とやってしまってなんとかなっても、後で必ずいい加減にやったことは自分に返ってくる。頑張らないと思わされる瞬間です。
だからこそ、残りの学生生活は、後悔しないように今までの2倍、3倍濃い充実した時間したいと思っています。
将来は、住宅メインの空間デザイナーになりたいです。最初はリノベーションができる会社で働いてリノベーションのノウハウを学んで、その技術を持ってさらに上を目指したいです。

竹谷 円さん
グラフィック専攻
真剣に向き合いデザインに対する「思い」が変った
創造社を選んだのは、先生との距離がここは近いと感じたから。学校見学に来た時、ただ見学に来ただけの私とも真剣に話を聞いて応えてくれ、たぶん在学生になってもこれよりさらにいい関係で学べると思いました。
学び始めて変わったことは、デザインに対する「思い」。高校のクラブでもデザインをしていたけど、妥協していたと思います。「まぁ、いいかな~これくらいで」みたいな?
「思い」が変わったと感じたのは、1年生の最後に挑んだ進級制作の時でした。
企画からデザインまでを1から自分でやらなくてはいけなくて、とにかく忙しかった。「続ける」ことを題材にしたフリーペーパーを企画し、取材からデザインまでをやったのですが、特にインタビューが大変でした。やってみないとわからない事だらけで、でも自分が企画したから妥協したくなくて。「経験を積んでデザインができる」とも感じました。
残りの学生生活は、「学生を楽しむ!」。「やりたい」ことを一緒にやりたい今の仲間と悔いが残らないようにしたいです。将来はわからないけど、「今を大事に」していきたいです。

池田 真尋さん
ディスプレイ専攻
妥協しなかった人だけが見れる「デザインの世界」があることを知りました。
創造社を選んだのは「課題が多い」と聞いていたからです。大学での就活で内定をけってまで再チャレンジすると決めたので、それなら「とことんやりたい」と思いました。
最初はやっぱり課題が多くてしんどかったです。そのおかげでスケジュール管理がうまくなりました。今までは、決まり決まったスケジュールの中で必然的にスケジュールが埋まっていく感じ。でも今は、「いつ」「どこまで」「どのくらい」課題をこなしていかないといけないかを自分でコントロールし、自分の責任で管理していかなければ行き詰まってしまいます。常に自分に厳しく!私以外のクラスメイトも働きながら頑張って学んでいる人が多い環境だからこそ、頑張れていると思います。
あとは、限界を超えた先に見えてくるものがあることを知りましたね。今までは、「そこそこ」合格ラインみたいなものが見えていて、そこまでいったら「まぁ、いいか」と。でも先生方はその先に行けと指導されるので、自然と「まだまだ」「もう少し」とさらに上を目指すようになりました。それを強く感じたのは進級制作です。最終、選抜に選ばれ公開プレゼンテーションで学科のトップである「学校賞」を争うことに。特にプレゼンテーションは得意だったので、当日のプレゼンテーションとそれに使うPDFに最後の力をつぎ込み、狙い通り「学校賞」をいただきました。まさに「最後まで頑張り抜いたヤツが残るんや」という先生の言葉を実感した瞬間でした。
学生でいられるのも後わずか。今しか学べないことを妥協せずしっかり学び、創造社で得た仲間との時間を大切にしたいです。
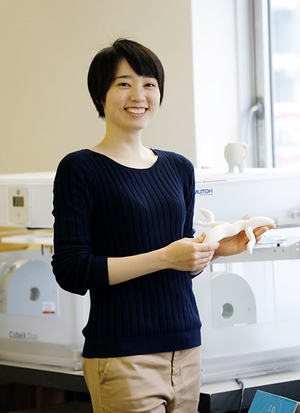
福永 愛美さん
プロダクト専攻
職人さんや使う人が大切にしたくなる「道具」をデザインするデザイナーになりたいです。
以前は事務職で働いていました。職人さんがいる職場だったので、職人さんがいつも自分たちの使う道具を大切に扱っている姿を見て、「私も職人さんに大切にされるような道具を創る人になりたい」という気持ちが湧いてきました。
そんな時に目にした「AIに仕事がとられる」という記事が再進学を決意させました。なぜなら私がやっている事務職はまさにAIにとられる仕事だったからです。
国の制度である教育訓練給付金制度の対象でもあったことから、夜間部でもこの制度が使える創造社を選びました。昼間部にしなかったのは、もちろん夜間部の方が学費が安かったことと夜間部の方が同じような再進学者が多いのではと思ったからです。
入学して最初はデザインの基礎が多く、もどかしい思いをしました。今になれば基礎が大切だったとは思えます。何を見るにも「なんでこのカタチなんだろう?」「ターゲットはだれ?」「コンセプトは?」と自然に考えるようになったのも、入学してから。「GUI演習」では、人がモノを使う時の行動を分析して、その行動に対してどういう「見え方」「使い方」をしていて、もっと合理的に目的を達成できるカタチやデザインはないのかを学びました。
創造社での学びをしっかり吸収して、きっかけになった職人さんや使う人が大切にしたくなる「道具」をデザインできる、まっすぐ「芯」が通ったデザイナーになりたいです。

大浦 イッセイ先生
プロダクトデザイナー/工業デザイナー
日本インダストリアルデザイナー協会委員
同JIDAサロン委員会委員長
大阪デザイン団体連合議員
デザイナーは日々が勉強
一般的にデザインといえば、単に色、柄、形を時代のトレンドに合わせて表現する仕事と思われていますが、私が生業とするプロダクトデザインの仕事は、人が困っていることや改善が必要なことを「知る」「見つける」ことから始まります。素材、技術、ノウハウなどのエンジニアリングの知識、ブランディング、マーケティング、ビジネスモデルなどのソーシャル領域の知識、また知的財産権などのリーガル領域の知識までインプットした上で、人の意識まで変えるようなデザインをしています。プロダクトデザイナーがすべて私のようにインプットしているわけではありませんが、少なくともデザイナーは日々が勉強です。皆さんとともに学び、最先端の情報を皆さんと共有できればと思います。

青木 一成先生
アルファテクトアソシエイツ 主宰
建築設計・インテリアデザイン・行政のまちづくりの企画コンセプト創りの他
「デザイン」に境界線はない
街はデザインの宝庫です。普段、何気なく通る道に、何となく入った店に、いつも使っている文具に…皆さんの身の周りには実に多くのデザインが転がっています。どのような業界をめざすにしろ、「デザイン」に境界線はありません。
自分の専攻分野ばかりに囚われず、広い視野と好奇心を持って街と接すると、とても多くの事を吸収する事ができます。いろいろな物に興味を持ち、いろいろな事を探求し、常に自分自身の「デザイン脳」を刺激していきましょう。
それが、いつか必ず皆さんの財産となる事でしょう。

荒畑 肇先生
荒畑商環境デザイン研究所 主宰
金属工芸・照明・インテリア・建築・複合商業施設
計画から街づくりまで。日本商環境設計家協会会員
関西インテリアプランナー協会会員
物や空間を通して問題解決を行い、利用者の自己実現の欲求に応える事
デザイン業をめざすみなさんは、この道に進もうと思った時、ここには“何か”があると感じ考え行動に移された事と思います。その“何か”は人それぞれ異なりますが『何かがある』という事を信じて行動に移された事は確かで、この事は、今後みなさんが、デザインの仕事を行っていく上で重要なキーワードの1つになると考えています。つまり、これからの仕事は、生活者に『何かがある』と感じさせ、いかにして行動に結び付けさせる事ができるかを考える事であり、物や空間を通して問題解決を行い、利用者の自己実現の欲求に応える事を考え、実行し続ける事になるからです。私は、今後も考え続けたいと思っています。
きっとこの学校が好きになる!進路選びの第一歩はここから
-
30秒でカンタン
無料 パンフレットをもらう
もっと学校について知るなら🙌

圡井 麻奈実さん
2年制コトづくり系
作る時間より「考える」時間の方が はるかに多い
同世代で騒ぐ感じがあまり好きではなかったので、年上の人もいる創造社の落ち着いた雰囲気が気に入りここに決めました。
高校時代とは違い、デザインを軸に自分とはタイプの違う友達ができ、はっきりと意見を言い合い指摘し合える仲間ができたと感じています。1年生の最初のデザインの基礎はとにかく課題数が多くて大変でした。2年生になってからは、「コンセプト」などを考えることに時間がとられ、とりあえず課題数をこなすだけの1年生とは違う大変さを味わっています。デザインするということは、作る時間より「考える」時間の方がはるかに多いことを知りました。
2年生で迎える最終の卒業制作では、進級制作を超える作品をつくりたいと思っています。それだけではなく、この後も自信を持てる作品を増やしていけるよう頑張ります。