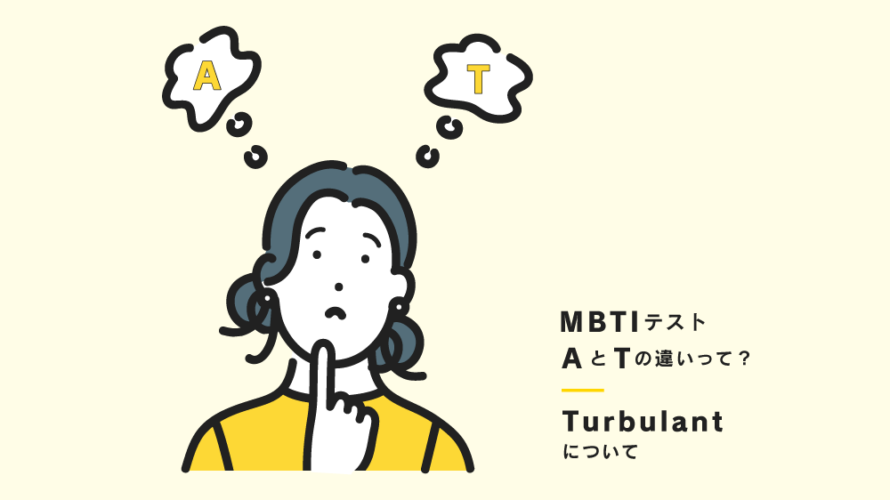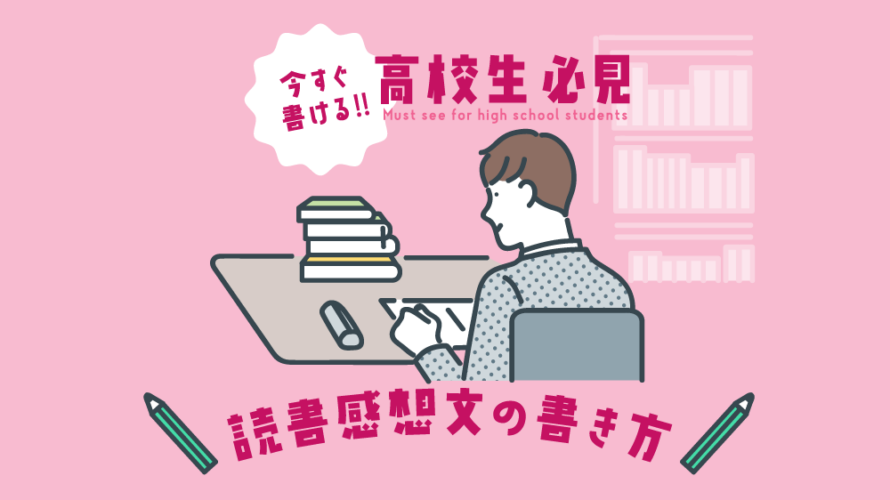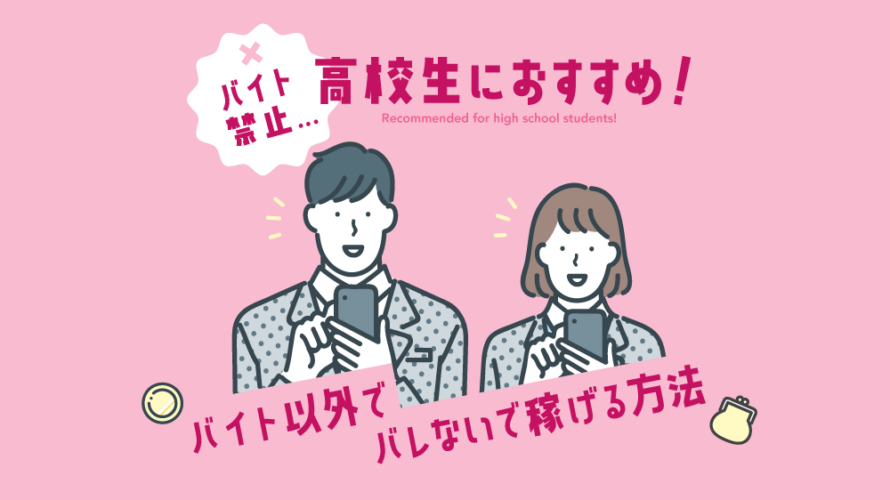建築設備士になるには?仕事内容や必要な資格、将来性などを紹介!
- 2020.12.04

記事をシェアする
この記事は約 5 分で読めます。
快適な室内環境、安全な電気設備、衛生的な給排水設備…。
私たちは、普段何気なく過ごしていますが、建物内の快適さや安全は、さまざまな建築設備によって支えられています。
そして、これらの設備を設計・管理するのが、建築設備士です。
建築設備士は、建築法に基づく国家資格で、建築物の安全性や機能性を確保するために、高度な専門知識と技術を駆使して活躍しています。
建築設備士の資格を取得すると、建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の受験資格が得られたり、設備設計一級建築士の講習受講資格が得られたりするなど、キャリアアップに繋がる多くのメリットがあります。
この記事では、建築設備士の仕事内容や、資格を取得するメリット、将来性、年収、向いている人の特徴、さらにおすすめの専門学校まで、詳しく解説していきます。
建築に興味のある方や、建築設備士の仕事に就きたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
建築設備士とは?
建築設備士は建築法に基づく国家資格です。
建物に備え付けられている建築設備の専門知識や技術を持っているため、建築士に対して建築設備の設計や工事管理に関する助言を行うことができます。
建築設備士の資格を取得することで、次のようなメリットがあります。
・一級建築士の受験資格を得ることができる(免許取得には建築設備士として実務経験を4年以上が必要)
・建築設備士資格と一級建築士資格を両方持っている場合は設備設計1級建築士(一級建築士の上位資格で設備設計のスペシャリスト)の講義受講資格である「一級建築士として5年以上設備設計の業務経験を有するもの」の「業務経験」に、建築設備士として行った業務経験を含むことができる。また、一部講義が免除される
・1年以上の実務経験を有する建築設備士は、専任技術者(請負契約の締結の際の技術的なサポートを行う)や主任技術者(現場において技術上の管理、監督を行う)の資格を得ることができる
建築設備の複雑化・高度化や、建築物の安全性に対する意識の高まりから、建築設備士の重要性が増しています。建築設備士は、高度な専門知識を有することが求められます。
建築設備士の仕事内容とは?
建築設備士は建築設備全般に関わる専門知識と技能を持っています。
主な仕事は建築士に対する建築設備の設計や工事管理のアドバイスで、例えば電気設備や給排水設備、空調設備の設計などを行います。着工後は現場で工事の管理や指導を行います。
実際は建築するにあたって必ずしも建築設備士が必要というわけではありません。
建築設備士がいなくても建築設備の工事などをすることができるのですが、きちんと建築設備士から助言を受けている場合は建築確認書などの公的書類に建築設備士の名前を記載することが義務づけられています。
建築設備士の助言を受けることで、建築物の安全性や品質の向上が期待できます。建築設備は複雑化・高度化しているため、建築設備士の需要はますます高まっています。
建築設備士になる方法(資格取得方法等)
建築設備士になるには公益財団法人建築技術教育普及センターが実施する建築設備士試験を受験・合格する必要があります。
建築設備の安全性や品質を向上させるための助言をするという役割からわかるように、高度な専門知識や技術が求められるため、受験資格も厳しく設定されています。





建築設備士試験と難易度について
では、建築設備士試験の概要をチェックしていきましょう。
当試験の合格率は第一次試験が約30%、第二次試験が約50%となっており、全体の合格者は20%以下となっています。その理由としてメジャーではない資格なのでモチベーションを保ちにくいことなどが挙げられるようです。中には一級建築士試験よりも難しいという人もいるほどだと言います。
しかし、この資格を取得することによって建設業界における信頼度がアップするため、就職や転職にも有利になります。前述したメリットもありますのでキャリアアップもしやすいでしょう。そのため建設業界で働くのであれば取っておきたい資格とも言えます。
(1)大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者
(2)一級建築士等の資格取得者
(3)建築設備に関する実務経験を有する者
※(1)~(3)それぞれに応じて建築設備に関する実務経験年数が必要
【受験可能になる保有資格】
・一級建築士
・一級電気工事施工管理技士
・一級管工事施工管理技士
・電気主任技術者(第一種、第二種又は第三種)
・空気調和・衛生工学会設備士
【必要な実務経験】
・上記の資格保有者…資格取得の前後を問わず実務経験2年以上
・四年制大学の指定科目(建築・機械・電気)卒業の場合…実務経験2年以上
・短期大学、高等専門学校、旧専門学校の指定科目(建築・機械・電気)卒業の場合…実務経験4年以上
・高等学校、旧中学校の建築・機械・電気卒業の場合… 実務経験6年以上
・その他 学校・専攻により …実務経験2~6年以上
・学歴や資格がない場合…実務経験9年以上
【実務経験に認められるもの】
・設計事務所、設備工事会社、建設会社、維持管理会社等での建築設備の設計・工事監理(その補助を含む)、施工管理、積算、維持管理(保全、改修を伴うものに限る)の業務
・官公庁での建築設備の行政、営繕業務
・大学、工業高校等での建築設備の教育・研究
・大学院、研究所等での建築設備の研究(研究テーマの明示を必要とします)
・設備機器製造会社等での建築設備システムの設計業務
受付期間:2月下旬~ 3月中旬
※原則として「インターネットによる受付」のみ
試験日程:
第一次試験(学科)…6月下旬
第二次試験(設計製図)…8月下旬
試験地:
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪府、広島市、福岡市、沖縄県※
※沖縄県については、第一次試験(学科)のみ実施。
また、沖縄県で第一次試験(学科)を受けた受験者については、原則として、福岡市を第二次試験(設計製図)の試験地とする。
試験科目:
第一次試験(学科)
・建築一般知識(建築計画、環境工学、構造力学、建築一般構造、建築材料及び建築施工)
・建築法規(建築士法、建築基準法その他の関係法規)
・建築設備(建築設備設計計画及び建築設備施工)
・建築設備
第二次試験(設計製図)
・建築設備基本計画(必須:建築設備に係る基本計画の作成)
・建築設備基本設計製図(選択:空調・換気設備・給排水衛生設備または電気設備のうち受験者の選択する1つの建築設備に係る設計製図の作成)
合格発表:
第一次試験(学科)…7月下旬
第二次試験(設計製図)…11月上旬
建築設備士に関連する資格
●建築士
建築士は一級建築士・二級建築士・木造建築士の総称で、建築物の設計や工事管理、建築確認申請などを行う専門職です。
一級建築士は制限なく設計することができますが、二級建築士や木造建築士は延べ床面積の制限や高さ制限、素材の制限などがあります。
●施工管理技士
建設現場には大工やとび職など、多くの技術者が集まります。
施工計画に基づいて、工事を計画通りに施工するために人をまとめたり工程や品質の管理をしたり、安全管理をしたりと全体の管理業務を行うのが施工管理技士です。
建築設備士の将来性
建築設備士は、建築物の安全性、快適性、省エネルギー化に貢献する専門家です。
近年、建築物は高度化・複雑化し、地球環境問題への意識も高まっています。さらに、老朽化建築物の増加や災害リスクへの対応も求められています。
このような状況下で、建築設備士の役割はますます重要になっています。具体的には、高度な情報通信技術やエネルギー管理システムなどを統合的に設計し、省エネルギー化や環境負荷の低減に貢献します。
また、老朽化建築物の維持管理・改修や、防災・減災の観点からも重要な役割を担います。
2015年の建築基準法改正では、高さ2,000メートルを超える建築物には、建築設備士による助言が義務付けられました。これは、建築設備士の専門性が社会的に高く評価されていることを示しています。
これらのことから、建築設備士は、今後も高い需要が見込まれる、将来性のある職業と言えるでしょう。
建築設備士の就職先
建築設備士の主な就職先には次のような場所があります。
・建設会社
・設計事務所
・建設コンサルタント
・不動産会社
・ビル管理会社
・保全会社
・建設設備メーカー など
建築設備士の平均年収・MAX年収
建築設備士の平均年収は約720万円で、日本人の平均年収は約440万円であることと比較するとかなり高額だと言えます。
もちろん就職先によって異なりますので、大手企業や大手メーカーは高収入で、下請けをしている中小企業は低めの傾向です。
中には一級建築士の資格などと併せて取得して専門性を増すことでかなりの高収入を得ている人もいます。経験豊富な建築設備士であれば、1,000万円を超える年収を得ることも可能でしょう。
建築設備士に向いているのはこんな人
建築設備士は、建物の快適性、安全性、省エネルギー化を担う仕事です。
責任感と専門知識を持ち、さまざまな人と協力しながら仕事を進めることが求められます。
具体的には、以下のような人が向いています。
・物事を論理的に考え、問題解決能力や分析力に長けている人
・責任感が強く、細心の注意を払って仕事に取り組める人
・コミュニケーション能力が高く、協調性のある人
・好奇心旺盛で、常に学び続ける意欲のある人
・体力に自信があり、現場での作業にも対応できる人
これらの特徴に多く当てはまる人は、建築設備士として活躍できる可能性が高いでしょう。
建築設備士に関連する職業





建築設備士に関連するおすすめの専門学校
ここからは、おすすめの建築設備士に関連する専門学校をご紹介します。
いずれも建築に関連する分野でとても評価の高い学校なので、建築設備士について専門的に学びたいという方には最適な学校です。
修成建設専門学校【大阪府大阪市】
◆関連学科:建築学科、建築施工学科 ※2024年4月に住環境リノベーション学科から名称変更、専科 1級建築士科 2021年設置
建築・インテリア・土木・造園のスペシャリストをめざす!
修成建設専門学校の詳しい紹介はこちら専門学校 東京テクニカルカレッジ【東京都中野区】
◆関連学科:建築監督科、建築科、建築科(夜間 建築士専科)
建築・インテリア・IT・ゲーム・Web・環境・バイオ分野のプロに!
「わかる」だけでなく、「できる」ようになる11学科。
金沢科学技術大学校【石川県金沢市】
◆関連学科:建築学科
金沢科学技術大学校(通称:Kistキスト)は、昭和62年に北陸唯一の総合工業系専門学校として創立。以来、多くの卒業生が北陸を中心とした産業界において、技術者として活躍しています。
金沢科学技術大学校の詳しい紹介はこちら穴吹デザイン専門学校【広島県広島市】
◆関連学科:建築学科
広島で30年以上の歴史をもつデザインの専門学校。
グラフィック、イラスト、写真、マンガ、アニメ、ゲーム、映像、企画、プロダクト、家具、アクセサリ、インテリア、建築などが学べるデザイン学校です。
麻生建築&デザイン専門学校【福岡県福岡市】
◆関連学科:建築士専攻科、建築学科、建築学科〈夜間〉、建築CAD科、インテリアデザイン科
私たち「夢」叶える宣言!
麻生建築&デザイン専門学校は〈建築分野〉 と 〈デザイン分野〉を学ぶことができる専門学校です。
富山情報ビジネス専門学校【富山県射水市】
◆関連学科:建築・デザイン学科 建築士専攻、建築・デザイン学科 建築CAD専攻、建築・デザイン学科 空間情報専攻
好きをカタチに、
生きるチカラに。
サイ・テク・カレッジ那覇【沖縄県那覇市】
◆関連学科:建築デザイン科
建築デザイン科で最先端の技術と資格を取得でき、スペシャリストを育成する沖縄の専門学校です。
サイ・テク・カレッジ那覇




記事をシェアする


 専門学校を探す
専門学校を探す
 職種から探す
職種から探す
 特徴から探す
特徴から探す
 学費制度から探す
学費制度から探す
 資格・職業を考える
資格・職業を考える