
日本文化の研究を深化させるとともに、異文化との比較・相対化を通して、日本文化を世界へ創造的に発信することのできる人材を育成する
- 募集定員
-
日本文学科:250名
中国文学科:60名
外国語文化学科:120名
史学科:190名
哲学科:65名
- 修業年限
-
4年
- 初年度納入金
-
入学金:240,000円
授業料:760,000円
施設設備費:210,000円
維持運営費:10,000円
若木育成会費:29,000円
若木学友会費:5,300円
若木学友会入会費:1,000円
國學院雑誌代:2,000円
院友会入会金:10,000円
國學院大學は、明治十五年(1882)に設立された皇典講究所をその母胎・前身とし、国史・国文・国法を専修する学校として構想された経緯があります。
文学部は、その皇典講究所設立の精神や研究・教授の歴史と伝統を直接に担う学部であり、文学部の歴史は本学の歩みそのものであるともいえるでしょう。
そのような歴史と伝統とを背負いながら、文学部はいま、新たな試練に直面しています。
すなわち近年、大学の学問研究と教育とに対する社会の要請は、ますます強まっていく国際化・高度情報化への対応、生涯教育機能の強化、学際化への対応、学術研究の高度化への対応を求めています。
文学部においてもこうした要請に応える組織と教育内容の充実に積極的に取り組んでいかなければなりません。
組織と教育内容の充実という動きは、文学部の学科構成の再編成、いわゆる一般教育課程の見直し・再編成という形で、一つの結実をみました。
すなわち、平成七年度からの教養総合カリキュラムの導入、平成八年度の文部省認可による文学部(第一部)の神道学科、日本文学科、史学科、中国文学科、哲学科、外国語文化学科の六学科体制がそれです。
これらの学科および教職など各種資格課程、外国語・スポーツ身体文化・自然科学の各研究室は、さらなる新しい文学部像を模索し続けています。
そのあらわれが、平成十四年度の神道学科を母体とした神道文化学部の新設であり、平成十七年度からの日本文学科・史学科の昼夜開講制への移行です。
本学の創立百二十周年にあたる平成十四年には、神道文化学部の独立とともに、本学が、世界的な研究教育拠点の形成をめざした文部科学省の「二十一世紀COEプログラム」(人文科学)の拠点校に選定されたことも 、特記すべきことでしょう。
今後の文学部は、「教養総合」の理念をさらに発展させ、本学の中心的な役割を担う学部として、日本文化の研究を深化させると同時に、異文化との比較・相対化を通じて日本文化を世界へ創造的に発信することができる組織体として、各学科が有機的かつ緊密に連携する総合的な学部をめざすことになるでしょう。
そしてそのことは、世界的な研究拠点校に選定された大学としての責務でもあります。
みなさんは、こうした現況にある文学部に身を置き、その一員として、研鑚を積もうとしているのです。
専攻・コース一覧
-
日本文学科

- 募集定員
-
250名
- 修業年限
-
4年
<日本文学科>
明治15(1882)年に創立された皇典講究所の伝統を踏まえ、古代から現在に至る日本の文学・言語・風俗習慣・儀礼などの研究を通して、日本文化を総合的・体系的に捉えつつ、今を生きる私たちの創造の指針となることを目指します。
2年次には「日本文学」「日本語学」「伝承文学」のいずれかの専攻に分かれます。
<カリキュラム>
日本文学科には、日本文学専攻・日本語学専攻・伝承文学専攻があり、専攻によって専門教育科目の履修方法が異なります。
また、各専攻に属しながら、日本語教育・国語教育・書道・表現文化の各領域科目も適宜履修できます。
日本文学科のカリキュラムは以下の4種類に大別されています。
1.学科基幹科目:日本文学科の学びの中心となる科目群です。
2.展開科目:各専攻分野の発展的な内容を扱う科目群です。
3.関連科目:日本文学科の学びに関連する他学科開講の科目群です。
史料講読ⅠⅡ、中国学入門、中国文学通史、中国古典読法基礎など
4.卒業論文
4年間の勉学と研究の総まとめとして、卒業論文(8単位)を提出しなければなりません。
卒業論文は、3年次・4年次の2年にわたり取り組むことになります。
そのため、早めに卒業論文のテーマと指導教員を決める必要があります。
日本文学科では、下記のスケジュールでガイダンス、指導等を行っています。
(3年次)
4 月 卒業論文の予備題目(仮題目)提出や指導教員確定に向けてのガイダンス
5 月 指導教員の決定及び予備題目の決定(書類提出)
7 月 指導教員の指示のもと、基礎的研究を行う
10月 第1次題目の提出
指導教員の指示のもと、第2次題目提出に向けて発展的研究を行う
(4年次)
6 月 第2次題目の提出(題目の最終確定、以後変更はできない)
指導教員の指示のもと、卒業論文作成の準備
概要作成・書式確認・目次作成・下書作成などを行う
12月 卒業論文の提出 -
中国文学科

- 募集定員
-
60名
- 修業年限
-
4年
<中国文学科>
中国の古典から近現代文学まで、中国文学を広く学びながら、世界に通じる広い視野と豊かな人間性を育成することを目指しています。
2年次には、各自の関心や目的に応じて「文学研究」「中国語教養」「中国民俗文化」「人文総合」の4プログラムから一つを選択します。
<カリキュラム>
中国文学科では、「何をやりたいか・何を身につけたいか・何を知りたいか」という就学前の視点に立って、学科の科目を組み上げました。
多くの大学では、学問分野によって専攻やコースが提供されていますが、未知の専門分野からイメージして、進路を選択するのは難しいのではないでしょうか。
本学科では、「興味と志望」を大切にします。入学前・入学後・進級後と、どの段階でも自分の関心にしたがって「選べる」ことを重視して講義をプログラミングしました。
1年次はすべてのプログラムの導入的な各概説を受講し、2年進級時に選択します。
また、副専攻の制度を使えば、他学部他学科が提供するさまざまな学問にもアプローチできます。
◎学科カリキュラムは、次の3種類に大別されています。
1.学科基幹科目
学科基幹科目は、A《学修基礎科目》、B《学科基礎科目》、C《学科応用科目》に分かれ、学科専門教育の根幹をなし、基礎力の修得から応用力の養成までを目指します。
2.プログラム専修科目
プログラム専修科目は、A《導入科目》、B《プログラム基礎科目》、C《プログラム応用科目》に分かれ、文学研究プログラム・中国語教養プログラム・中国民俗文化プログラム・人文総合プログラムに共通する基礎力を養います。
3.関連科目
関連科目は、日本文学科の科目ですが、主に国語科教員を志望する者に必須とされる日本文学概論1)・2)、日本語学概論1)・2)が置かれています。
学修基礎科目の中の中国古典読法基礎、および関連科目は自由選択の科目です。修得単位は、全学オープン科目(24単位)に算入されます。 -
外国語文化学科
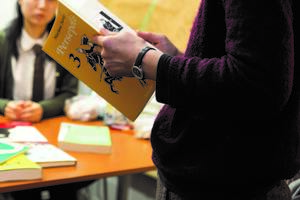
- 募集定員
-
120名
- 修業年限
-
4年
<外国語文化学科>
外国の言語と文化を総合的に学修し、日本文化と外国文化の差異や共通性をグローバルな視点から理解すると同時に、異文化と積極的に交流しながら文化摩擦の解消を図るコミュニケーション能力を養います。
2年次には「外国語コミュニケーション」と「外国文化」のいずれかのコースを選びます。
<カリキュラム>
◎2つのコース
外国語文化学科には、「外国語コミュニケーションコース」と「外国文化コース」の2つのコースが設置されています。
「外国語コミュニケーションコース」は、必修外国語(英語)および選択外国語(ドイツ語・フランス語・中国語)のコミュニケーション能力を徹底的に養い、主体的な異文化コミュニケーションを実践できる人材の育成に重点が置かれるコースです。
「外国文化コース」は、学際的・総合的に外国文化を学び、国際社会において主体的に活躍できる人材の育成に重点が置かれるコースです。
1年次では外国語文化学科の学生全員が両コースの学問領域を概括的に学び、2年次から各自がそれぞれのコースに分かれて専門的な学習を進めます。
<外国語基礎演習・外国語演習>
1年次から4年次まで配置されている外国語演習科目は、ネイティブ・スピーカーと日本人教員が担当し、「読む・書く・聞く・話す」の4つの技能の習得を目指します。
とくに「英語演習Ⅰ・Ⅱ」では英語を基本的に「聞く・話す」技能、「英語文献演習Ⅰ・Ⅱ」では英語を基本的に「読む・書く」技能の習得に重点が置かれます。
選択外国語(ドイツ語・フランス語・中国語)に関しても、1年次・2年次の外国語基礎演習科目においては、「読む・書く・聞く・話す」ために必要な基本的能力を徹底的に養うことに重点が置かれます。
さらに「英文法」では英文法の基本を再確認し、2年次の「英語表現」・「ドイツ語表現」・「フランス語表現」・「中国語表現」では、各国語のコミュニケーション技能の実践的・総合的習得を目標とします。
3年次と4年次の外国語演習科目については、総合的な言語運用能力の向上に重点が置かれます。
なお、外国語コミュニケーションコースには、外国語基礎演習2科目4単位が多く割り当てられています。 -
史学科

- 募集定員
-
190名
- 修業年限
-
4年
<史学科>
3年次に選択する「日本史学」「外国史学」「考古学」「地域文化と景観」の4コースそれぞれに、2年次に選択する一般企業や公務員としての就職(S-プログラム)、大学院進学や教職・学芸員としての就職(P-プログラム)の2プログラムを設定したカリキュラムを導入しています。
より明確になった研究対象とキャリアデザインに基づいた学びを実践しています。
<カリキュラム>
史学科は、文字資料ならびに考古資料・文化遺産・文化景観などの非文字物質資料を駆使して過去の人間社会・文化とその歴史を明らかにし、歴史遺産の継承と活用を通した社会と文化の豊かな想像を追及するとともに、研究・分析の過程で修養される「歴史的思考」を身につけた、社会に有用な人材を育成することを目的とする。
史学科には「日本史学」「外国史学」「考古学」「地域文化と景観」の4つのコースがあり、それぞれのコースによって専門教育科目の履修方法が異なる。
史学科の専門教育の基幹となる2・3・4年次の演習は、きめ細かい指導を徹底するため定員制をとる。
また各コースには、将来の進路設計によってStandard Career Program(S-プログラム)とProfessional Career Program(P-プログラム)が用意されており、プログラムごとに履修すべき科目が異なっている。
学生は、自分の興味・関心に従っていずれかのコースを選択し、かつ将来どのような職業に就きたいかという観点からどちらかのブログラムを選択し、履修規程に基づいて単位を修得しなければならない。
また、さまざまな言語で書かれた史料や論文の読解に加え、国際的な発信力とコミュニケーション能力を修養することが、これからの史学科学生にとって必須の資質になるとの教学方針から、選択必修科目として第二外国語を課している。
<史学科の4コース>
・日本史学コース
・外国史学コース
・考古学コース
・地域文化と景観コース -
哲学科
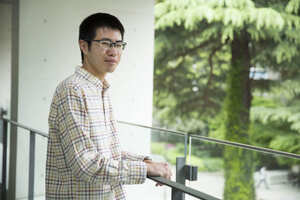
- 募集定員
-
65名
- 修業年限
-
4年
<哲学科>
西洋哲学思想の研究を中心に、インド・中国・日本の思想や、美と芸術の理論的考察などについて、総合的に学修します。
そして学生諸君の知的興味に応えるべく、あらゆるものを考える対象にして、多様なものの見方を学びます。
3年次には「哲学・倫理学」「美学・芸術学」のいずれかのコースを選びます。
<カリキュラム>
◎哲学・倫理学コース
古代ギリシア以来、批判的に吟味されつつ継承・展開されてきた哲学の精神を、現代に生きる者として、どのように批判し、理解し、そして受容するかをまず学びます。
哲学概論、哲学史というもっとも基本的な学説の講義をはじめとして、倫理学、論理学、宗教哲学、科学哲学、言語論、インド思想史、日本思想史、そして現代哲学など、多岐にわたる哲学的知識を探るとともに、特殊講義においては具体的なテーマ、あるいは哲学者・思想家に焦点を絞りながら問題を掘り下げます。
ギリシア語、ラテン語、サンスクリット語といった古典語(初級・中級)の授業が開講されているのも大きな特色です。
また自発的・創造的な知的訓練の場として、基礎演習、演習の授業が置かれています。
それらは学生各自の哲学的思索を真理へといざなうものであり、その集大成が卒業論文です。
◎美学・芸術学コース
美学は、西洋哲学の一分科として成立しましたが、諸芸術の動向の理論的・史的考察との関連において独自の展開を見てきました。
この美学と、具体的な諸芸術ジャンルの理論的考察としての芸術学、史的・実証的研究としての美術史とを視野に収めるためのコースです。
しかし、美学・芸術学コースだからといって、芸術作品だけが研究対象というわけではありません。
目に見えるすべての現象を対象として、ものを考える力と想像力を育成します。
基礎的科目のほか、特殊講義では西洋美術史、日本美術史、東洋美術史、音楽史、映像論、舞踊論、建築論などさまざまな芸術ジャンルについて学びます。
演習は純粋に美学理論的なものから個別芸術学的なものまで、特定のテーマを徹底的に掘り下げ、卒業論文に役立ててゆきます。
なお、さらに勉学を進めたい学生のために、大学院文学研究科史学専攻のなかに美学・美術史コースが置かれています。













